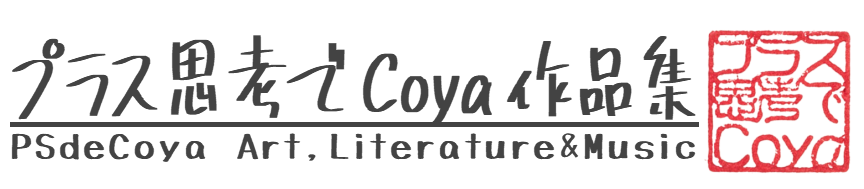無敵のチー牛、今日も行く。
芋堀り哉無敵のチー牛、今日も行く。
発達障害者である。陰キャのチー牛である。それは否定できない絶対的な事実として存在している。自分は違う、正常な人間だとどれだけ思おうとも、それを変えることはできないのだから、あきらめて、認めて、受け入れていくしかない。
ふっきれて開き直り、発達障害の陰キャチー牛としての人生を全うしていく。残念ながら、それしかない。
見方を変えれば、この境遇はもう守るものも失うものも何もない、無敵の人である。仕事での出世などありえないし、養うべき家族もいない。失敗しても、笑われるような恥をかいても、大きな痛手とはならない。傷も汚れも、全く気にならない、いつでもどこでもふらふらと行ける気軽な身分である。何をしたところで、世界には何らの影響も与えない、居ても居なくても変わらない、どうでもいい人間だ。
無敵のチー牛、今日も行く。それがこれからの生き方だ。体裁を整えようとか、自分を良く見せようとか、そんなことは目指さず、求めようともしない。そういった人生は、身分の違う健常者、上流階級の人々のものであり、君とは縁の無い世界である。君の人生は、陰キャのチー牛として、嘲笑され、馬鹿にされ、イジられイジメられながら、お道化て生きていくしかない。健常者様のストレスを発散するためのサンドバッグ、健常者様の出した汚物をぬぐいとるボロ雑巾。自分の体を汚損させることでしか意味や価値のない布きれ。
君は人間ではない。人間の皮を被った化け物。それを常に頭の片隅に置いて、それを常に意識しろ。
いみじくも明後日から、復職する。総務部付ということで、ほとんど要らないお荷物の役立たずであるわけだから、それにふさわしい恰好をしなければならない。
具体的にはこうだ。まず、ツーブリッジの金縁メガネとする。ヘアスタイルは七三分け、カラーワックスで色をグレーに染めて、ふけたおっさんの顔にする。ゲジゲジ眉毛で馬鹿みたいにデカい鷲鼻、手入れされていない前髪、覇気のない死んだ魚のような目、病気のような血色の悪い肌、シワとシミとたるみだらけの肌、これこそが正しい陰キャチー牛のあるべき顔である。
次に服装であるが、ダボっとしたサイズ感のダブルのスーツで、結び目の小さいダサい色柄のネクタイをタイピンで留めて、仕事中はアームカバーと緑色の指サックを装着する。小物として、セカンドバッグを持つ。アイテムもばっちり揃って、これで立派なチー牛の完成である。
言ってしまえば、コスプレや仮装のような、なりきりのお遊戯会である。責任ある社会人としての身なりではない。しかし、陰キャチー牛であることが誰の目にもはっきりとわかるよう、ヘルプマークや白杖、初心者マークなどと同様に、目印があるというのが大切である。こいつは陰キャチー牛の発達障害者ですよ、関わってはいけないキモい奴ですよとアピールする、ヤクザの刺青のような除け者の刻印、それが必要だ。
これこそが陰キャチー牛の正装、ドレスコードである。野球選手が試合の際にユニフォームを着るように、アイドル歌手がステージ衣装を着るように、陰キャチー牛もその服装を着ると、スイッチが入って全力を発揮できるようになる。
コスプレの効果は絶大であり、その恰好をすると、性格や言動も自然とそれにふさわしいものへと変化する。役を演じるように、それらしく立ち振る舞うこととなる。
ふざけている、調子こいているとの非難は必至だろう。でも仕方ない、発達障害者なのだから、どうやったって他人に迷惑をかけることとなる。存在自体が害悪なのだから、恰好もそのようなものにするのがよろし。
2024年9月29日
髪をグレーにしてみて
注文しておいたカラーワックスが届いたので、さっそく髪につけてグレーにしてみた。もっとベタベタして扱いにくいのかと思っていたが、案外簡単に塗れる。黒い髪が灰をかぶったようにグレーになっていき、あっという間にグレーヘアのおっさんに変身できた。
シルバーだともっと明るい色になって、黒髪とのギャップが大きくなるのだろうが、現実離れしすぎてアニメのキャラのような作った感じがする。年をとり、ふけて色素が抜けていったリアリティーがない。
ツーブリッジのメガネをかければ、鏡の中にいるのは紛れもないおっさんである。自分の顔ではないみたいだ。これはよい、おっさんに変身できる。
今日買ってきたダサいネクタイをタイピンで留めて、完璧におっさんになりきろう。
出勤が楽しみだ。
CoyaNote2024016
シャワーヘッドを買った。熊手か剣山みたいに固くてトゲトゲしていて、ゴシゴシと頭髪を洗っていける。汚れや皮脂、フケなんかをごっそりと落としていきたい。
さて、明日から10月、復職する。2回目の病休でもう出世など見込めるはずもないし、役立たずのお荷物、何もできない木偶の坊であるのは確かな事実なのだから、それをしっかりと自覚し、意識し、それらしく振る舞っていかなければならない。貼られたレッテルの通りの人物になるよう努力しなければならないのだ。
もう一度確認しておくと、ツーブリッジのメガネにグレーヘアの七三分け、細い結び目のネクタイをタイピンで留めて、仕事中はアームカバーと指サック。のろまでとろくてどんくさくて、ダサくてウザくてキモくてムカツク発達障害者のクズクソとして生きる。周りからは嘲笑と同情と憐みの目で見られ、あれよりはましだなと思われるような悪い見本、反面教師、必要な汚物という人生だ。それだ、それでいこう。
2024年9月30日
CoyaNote2024017
洗顔の際に耳の中に水が入ってしまった。ドロリとした粘性の液体が鼓膜に貼り付いて、不快感が甚だしい。頭を揺さぶると、ダブン、ダブンと重たい音を立てて鈍く響く。首を傾けてその場でスキップして水を抜こうとするが、なかなかうまくいかず、頭の中が不快な感覚で支配される。
2024年10月21日
CoyaNote2024018
ジェッソを塗ったけど、養生をしっかりやらないから、あちこち汚した。新聞紙から滴がポタポタと垂れて、いろんなものに付着してしまった。
トイレが詰まって、根本的に解決しようと、高圧洗浄機を買った。ホースや留め金などを追加で購入するために2回も同じ店舗を往復して、水が漏れてあちこち濡らして、悪戦苦闘してなんとか高圧の水を便器に向かって放出させたが、結局詰まりは解消せず、水を流すと便器からあふれてしまう。
ドロドロとした気分である。どうしようもない。
2024年10月27日
つけペンで書いてみて
昭和のおっさんサラリーマンになるべく、アイテムを充実させている。今回は、パソコンなどなく全て手書きだった頃、事務屋がこぞって使っていたつけペンを手に入れた。最新の技術が使われたコンテンポラリーなつけペンでも、マンガやイラストで用いられる本格的なつけペンでもない、昭和の時代に一般大衆の間で広く使用されていた日用品としてのつけペンを求めていた。ネットオークションで時代もののレトロなつけペンを2本、軸の色が黒と赤のものをセットで落札した。
ペン先とペン軸が入手できたところで、最も悩んだのがどのインクで書くかということであった。最初に考えていたのは、万年筆用のインクであった。使い慣れたメーカーのインクで、色や書き心地も勝手知ったるものであり、ガラス瓶も机上を飾る美しいオブジェとしての魅力がある。色も黒の他に赤、青、ブルーブラック、さらに最近は雅な名を持つさまざまな色のインクがあり、それらを気分で選ぶのは至福の楽しみであろう。
しかし調べていくうちに、どうもそうはいかないみたいだ。万年筆用のインクはあくまで万年筆用であり、つけペンでは使えないようだ。確かに昔、万年筆用のインクにガラスペンで書いてみたが、紙にのらず、かすれてうまく書けないことがあった。つけペンにはつけペン用のインク、モノクロ原稿なら製図用インク、カラー原稿なら証券用の瓶入りインクを用いるのが正しい。しかしこれらのインクは黒一色しか種類がなく、カラーヴァリエーションを展開させることができない。カリグラフィーをやるわけではないから、何色も必要なわけではないが、最低限黒と赤の2色のインクは欲しいところである。そのために、わざわざ黒と赤の2色のペン軸を用意したのだから。
インクの他には、墨汁もつけペンでは用いるという。硯に出さずとも、ボトルに入った開明墨汁という商品があり、これもマンガやイラストでよく使われるという。墨汁なら朱墨があり、これも同様にボトル入りのものがあったため、2色揃えることができる。求めるものに近いのは、インクではなく墨汁であった。
しかし、墨汁にもデメリットや懸念事項がある。墨のため、インクよりも乾くのに時間がかかるのではないかということや、墨だとペン先が錆びやすいこと、またガラス瓶に入ったインクというロマンなど、さまざまな要素が墨汁を選ぶことを妨げようとしていた。
それでも、そういった抵抗勢力を押さえつけて、強引に黒と朱のボトル入りの開明墨汁を購入し、実際にペン先を浸して、つけペンで書いてみた。感想としては、予想以上に良いというものだ。最初はペン先がなじんでいないのか、墨汁を吸い込まずに線がかすれてしまったが、書き続けていくうちに墨汁を充分に溜め込められるようになり、かすれることなくくっきりとした線が引けるようになった。墨汁のもちもよく、そう頻繁にペン先を浸さなくても、ある程度の量を書くことができる。すらすら、さらさら、かりかりと小気味よく紙に線を刻んでいく感触は、万年筆のそれと全く同じであり、デジタルでは絶対に味わえない手書きならではの楽しさである。書く前は、つけペンは面倒で手間がかかり、暇な趣味人の道楽か嗜みのようなものとの印象を抱いていたが、実際は全くもって手軽で、普通に使えるものであった。そうでなければ、パソコンが登場するまで筆記具の主流として日常的に使われてなかったであろう。昭和の時代では、つけペンを使うことは決して特別ではなかった。
乾きにくさと線のにじみについては、墨汁である以上はある程度受け入れなければならない。そもそも仕事においてつけペンで書くものが重要書類であるはずがなく、メモ書きやラフスケッチなど、落書きレヴェルの手遊びでしか出番はない。乾きにくくて線がにじんでしまうことも含めての、つけペンの味わいや楽しみととらえるべきである。考えてみたら、乾いていないインクや墨汁でシャツのカフスを汚さないために、アームカバーをしているのではないか。昭和のおっさんサラリーマンのアイテムは、飾りではなく意味と用途がある。
こうして、これからの筆記具が決まった。仕事で手書きをする際は、つけペンに墨汁で書いていくこととなる。添削などには朱墨を用い、文字通り朱書きする。これでまた一歩、昭和のおっさんサラリーマンに近付いた。
2024年10月29日
最近の制作についての考察
1. 二段階の絵の具の塗り
絵の具を塗る際に、あるべき形からはみ出し、混ざり合って著しく汚くなるという問題が長年あった。細い筆や割り箸ペンを使っても、効果はなかった。
今回、新たな技法を試してみた。絵の具を塗る際に、まずその色で輪郭線を引いて、次いでその中を同じ色で塗っていくという二段階の過程をとった。線描と面塗りで違いが出てしまうのではないかと懸念しており、実際にムラや筆致の方向などでうっすらと差異が見えるのだが、同じ色ということでよく溶かして混ざり合うようになだらかにすれば、許容できるくらいまでには均一になった。最後の仕上げに黒で輪郭線を引けば、この差異はほぼ気にならない。なによりも、これまでの色が混ざり合って、パサパサと擦ったような痕跡が出るあの極めて汚らしい画面を避けることができるのだから、この手法は大いに使える。これからの彩色は、このやり方で塗っていくこととしよう。
2. アクリル絵の具の上から墨汁で線描していく
カンヴァスの上に塗ったアクリル絵の具、これまでは輪郭線を引く際に油性のペイントマーカーを用いていたが、今回初めて墨汁を使ってみた。厚塗りのアクリル絵の具の上に、墨汁はかすれたり食われたりせずしっかりとのっかるかどうかが心配だったが、結果としては問題なさそうだ。墨汁の方が液体である分、そして筆で引く分、ペイントマーカーよりも自由度が高くなる。しかしそれは同時に、線の幅が一定とならず凸凹したり波打ったりして、きれいな描線を引けないという危険性も抱えている。実際、小さなカンヴァスに引いた輪郭線は、手の震えや力加減の下手さが如実に反映されてしまい、みみずがのたうちまわったような不器用なものとなってしまった。墨汁(あるいは水で溶いた絵の具)でペイントマーカーのように幅の均一な安定した線を引けることが、ずっと探求していたテーマであった。
3. 竹ペン
このような課題を抱えて、割り箸ペンやカラーシェイパーなどいくつかの道具を試していたわけだが、どれも求めていた成果を得ることはできなかった。
別件で昭和のおっさんサラリーマンを演じる中で手に入れたつけペンが、この課題を解決するヒントになるのではないかと仮説を立てるようになった。マンガやイラストでは、つけペンに墨汁やインキをつけて描線を引いて制作していくことから、これをアクリル絵の具にも応用できないかと考えたのだ。
意気込んでコミック用品のペン先を購入しようと画材屋の中を歩いていたところ、とある道具が目に留まった。竹ペンである。鉛筆程の太さの竹の先端を斜めに切り落とし、万年筆のペン先のようにスリットを入れたそれは、まさに求めていたものであった。計画を変更し、竹ペンと葦ペンを何本も購入した。
実際に使ってみた感想は、期待以上であった。つけペンのように、ペン先を墨汁や水で溶いた絵の具に浸すと、毛細管現象でスリットを伝ってインキが吸い上げられていく。スリットの先にある円いくりぬきの部分にインキが溜まると、ポタッと落ちることなく留まり続け、ペン先に一定の量のインキを供給していく。まさにつけペンと同じ感覚で、墨汁や絵の具の線描ができるのである。線の幅も、筆のようにふくらんだりかすれたりすることなく、一定の太さで安定的に引ける。割り箸ペンやカラーシェイパーのそれとは比べものにならないくらいインキのもちもよく、グラデーションにならずに均一の濃くくっきりとした線となる。これだ、これこそがずっと求めていた理想とする輪郭線である。これなら、細かい部分でも、ペイントマーカーと同じ質の線描ができる。答えは竹ペンであった。
この竹ペンで、墨汁はもちろんのこと、先ほど述べた二段階の絵の具の塗りも行っていける。これからの、社会人第3章の絵画は、竹ペンで墨による輪郭線が引かれた、今まで以上に精密なものとなる。
4. その他
その他として、変形カンヴァスについても書き残しておく。〇△♡の3種類の変形カンヴァスを以前に購入し、何を描こうかと迷っているままずっと放置していたが、今回描いてみた。
感想としては、矩形の時は意識しなかった画面の形が明確に強調されてくるため、構図を考えなければいけないというものである。△は頂点を上にすれば安定感、ピラミッドやヒエラルキーが強調されるし、逆三角形にすれば不安定さや動きが生まれる。今回のように頂点を右に配置すると、一点透視図法による遠近感が強調された構図となる。〇や♡も、その形に切り取ったことが殊更に強調される絵画を描かなければならない。
変形カンヴァスは、特殊な構図、表現の際に用いるのが有効である。
以上、秋晴れの文化の日に書き殴る。
2024年11月3日
CoyaNote2024019
病休から復職して早や1ヶ月。臨時職員どころかインターンや職場体験の中学生で十分な雑用しかしてない。居ても居なくても同じ、どうでもいい人。追い出し部屋の閑職で立派な窓際社員となった。
たまに内線電話に出ると、相手はまるで幽霊かゾンビにでも遭遇したかのように大きく驚き、間が空いてしまう。死んだはずのおめーが何で電話に出るんだよ、何でそこに居るんだよ、何でまだ働いてるんだよ、何でまだ生きているんだよ、さっさと成仏しろよと動揺を隠せないのが、数秒の沈黙からまじまじと感じられる。
もはや職場に居場所などなく、生きてもいない。成仏できずに留まり続けている怨霊みたいなものだ。周囲がそのように思っているのだから、その期待に応えるべく振る舞わなくてはいけない。キモイモンスターはキモイモンスターとしてキモイモンスターらしくあることが求められる。ツーブリッジの金縁メガネにアームカバー、無数のイボのついた指サックにセカンドバッグ、ネクタイピン、カラーワックスで染めた白髪、コスプレは完璧で、当たり前の様態として受け入れられている。それに更に磨きをかけなければならない。
失うものも守るものも出世も成長もなにもない、呼吸するだけの下等生物、そのように自分を作っていこう。
2024年11月3日
CoyaNote2024020
長らく悩まされ続けていたトイレの詰まりが、ようやく解消した。
2年前に美容クリームのボトルを誤って便器に落としてしまい、その時は流れたと思っていたのだが、ずっと排水管の入口に残っていた。それを核にしてトイレットペーパーやウンコが肉付けされ、排水管にフタをして詰まりとなっていた。いくらすっぽんさせても、高圧洗浄機で水を放出させても、異物が詰まっていては意味がない。
便器を取り外して、排水管の入口にウンコまみれのボトルを発見し、除去したところ、今までの詰まりがウソのようにすっきりと流れるようになった。練りがらし状の大量のウンコを見てしまい、頭にこびりつくトラウマとなった。
とにもかくにも、トイレの詰まりはこれで解消された。あたりまえにションベンとウンコができることが、これほどありがたいのかということを痛感させられた。体も健康になりそうだ。とても気分がいい。
これからは、異物落下に注意して、遠慮することなく、ウンコをしていこう。快眠快食快便、高級ダイヤを所持するより、ウンコが出ることの方が大事。
2024年12月4日
CoyaNote2024021
なにかを得るためには、なにかを捨てて犠牲にしなければいけないが、なにかを捨てて犠牲にしたところで、なにかを得られるわけではないのが辛いところだ。人生は等価交換とはいかず、損失だけの赤字というものもありうる。負債に意義や価値などなにもない。
沖縄へ行く、空を飛ぶ。
沖縄へ行く。紛れもない事実だ。この文章を書いている時点で、すでに飛行機の搭乗手続きも終わり、手荷物検査も通過して、今はロビーでお茶を飲みながら、出発時刻を待っている。あれだけ、飛行機が苦手で、遠くの旅行に出なかったのに、ここまで動けるだけのエネルギーやヴァイタリティ―があることが驚きである。
飛行機に乗るのはただの手段に過ぎず、沖縄に行くという目的さえあれば、なんらのためらいもない。思えば、目的のある旅行というものを今までろくにしてこなかったから、選択肢として飛行機に乗らなかったというのもあるのだろう。
沖縄に行く。それも、目的のある旅としてだ。手土産やプレゼントも用意して、大慌てでスーツケースや服もそろえて、とにもかくにも沖縄へ行く。そのことの意味や意義や価値など考えない、なんて猪突猛進の脳ミソ筋肉バカではいけない。したたかに、計算して、考えて、デザインしたシナリオに沿って物語を進めていく。これはそのはじまりだ。
2024年12月27日10:52
機内メモ
20分ほど遅れて出発。飛行機が離陸する瞬間はやはり緊張する。地上を走っている時のゆるんだのろのろ歩きは、滑走路に入った途端に一変し、強烈な重力と速度が体に襲いかかる。モニタで尾翼カメラの映像を見てみる。エンジンと滑走路の白いラインが偶然にも重なり、航跡のように見える。
離陸直後、前方からの陽差しが反射してプリズムができた。機体は虹の輪くぐりをして、沖縄へ向けて空を飛ぶ。
2024.12.27 13:15
CoyaNote2025001
リスカによって君の人生設計は
リスケを余儀なくされた
CoyaNote2025002
ONE FOR ALL
ALL FOR ONE
EXCEPT ME
答えは面相筆であった
絵の輪郭線をどのように引くのかが、長年の課題であった。ペイントマーカーを採用していたのだが、それに疑問を感じるようになり、水筆や割り箸ペン、竹ペンなどさまざまなものを試し、どれも満足のいく成果は得られなかった。
画材屋で見かけたのが、日本画で用いる面相筆であった。説明では、線描に最適であるとあったので、早速導入してみた。効果は抜群のものであった。細長い毛は鞭のようにしなり、直線もコーナリングも自在であり、墨や絵の具の含みもよく、途中でかすれることなく長い線を引くことができる。
考えてみたら、これまで墨で線描する際、書道用の小筆を使っていたのが間違いであった。文字を書くための筆と、線描するための筆は異なるものであり、その違いを意識せず誤った使用をしていたために、求める輪郭線を引けなかったのである。もっと早くに気付くべきであった。
面相筆という名称が、誤解を招く原因のようにも思えるが、日本画では他にも穂先がさまざまな形の筆を目的に合わせて使い分けていくようだ。平筆や丸筆などは洋画でも使うので知っているが、面相筆は中学生の美術の授業のデザイン画で使った際、その用途をしっかりと理解していなかった。
面相筆は大中小と3種類入手したので、太さによって使い分けができる。より太い線を引く場合は、丸筆や書道用の筆を用いればよいのだが、今後の方針として、輪郭線は太くせず、なるべく細いものを引いていく事を構想しているので、原則として面相筆のみを使うことにしたい。
ついでに、現時点で考えている今後の絵画の作風の方向性を書き連ねておく。
- 輪郭線は面相筆で細く引く
- 輪郭線は黒の場合は墨を使う
- 輪郭線の色は黒だけに限らず、場合によっては他の色(アクリル絵の具)も用いる
- 絵の具は少なくとも3回重ね塗りして平面的にする
- マスキングテープ、マスキング液、型紙を使用してベタ塗りする
- 腕鎮を使う
手間と時間をかけて丁寧に描くこと、それはおのずと制作ペースが落ちて作品数が減ってしまうわけだが、粗製乱造ではいけない。これからは一つの作品にじっくりと細やかに向き合って創作していくこととしたい。
2025年2月16日
CoyaNote2025003
エコバッグの中に、水筒と弁当箱を入れて出勤しているのだが、袋の中で収まりが悪い。細長い水筒が倒れたり、弁当箱が横転したりして、ぶくぶくと膨れ上がってしまう。統制や抑揚の効かない、カオスな中身、自分の頭の中や精神状態そのものである。
社会人第3章の画業の始まり
はじめに
新たな作風の模索が1年以上続き、さまざまな用具や技法を試して、そこから得られた知見について考察を行ってきた。プロトタイプとしていくつかの作品も制作したが、どれもこれが新たな画業の始まりであるとするには決定打に欠けていた。
試行錯誤の末、本日完成させた絵をもって、ここに社会人第3章の始まりを宣言する。
1. ジェッソの下塗り
カンヴァスにジェッソを塗るのは従前通りだが、これからは薄くしていく。何回にも何層にも塗り重ねてベタベタになったものではなく、余分な贅肉を削ぎ落とした下塗りの上に描いていく。
2. マスキング
下塗りした画面の上に輪郭線を引いてそこに彩色をしていく。最初に地となる背景から塗っていくのだが、その際、マスキングテープを貼り図となるモティーフのフォルムに沿ってナイフでカットして色がはみ出さないようにした。これがかなり効果的で、これまでのように色がはみ出してきれいに塗れないということがなくなり、幅広の平筆で均一的に背景色が塗れるようになった。地平線やテーブルなど、画面を分割する直線も、きれいにまっすぐ表出されるようになり、はみ出しを隠すために黒いインクで太く線を引いてセパレーションする必要がなくなった。
背景色を塗り終わった後に、マスキングテープを剥がしていくと、白ヌキされたモティーフのフォルムがきれいにくっきりと出現してくる。それはとても蠱惑的で鳥肌が立つほどゾクゾクする。
より丁寧に、細かくしていくのであれば、モティーフの各色、パーツ毎にさらにマスキングしていくことになるが、そこまでする必要はないと思う。ともかく、背景色をきれいに塗れるようになることが、大きな進歩である。
なお、マスキング液も選択肢としてあるが、今回使ったが乾燥が遅くてうまくマスクできなかった。導入にはさらなる検討を要する。
さらに、型紙の使用もありうる。今回は水玉模様を描く際に円く穴を空けた型紙を部分的に使用した。切り紙絵のように、各モティーフのフォルムに切り抜いた型紙を画面上に並べて、マスクしていく。多色多版摺りの要領である。次回作は、この手法で制作することとしたい。
3. パステルカラー
アクリルグアッシュのパステルカラーを使用した。アクセントとして一般色もいくつか塗ったが、全体的にほんわかとしたトーンで統一され、とても可愛らしい作風となった。他にメタリックカラー、パールカラー、ジャパネスクとさまざまなシリーズがラインナップされている。目指す作風、雰囲気によって最適なトーンを使い分けていきたい。
4. 輪郭線に墨
これまでは輪郭線を引く際に、三菱ペイントマーカーを使用していたが、これからは墨を用いていくこととする。
面相筆を使えば、細い線を引ける。まだ使いこなせていなくて、筆先をコントロールできずに、色と色との境目からずれてしまい、それを修正するために太くなってしまったが、鍛錬を重ねて求める通りの線が引けるようになりたい。ペイントマーカーで引いた線とは、確実に異なるものであり、それは作品全体の雰囲気を決定付ける大きな要素である。
また、油性マーカーではワニスを塗れないが、墨であればワニスを塗って画面を保護できる。艶ありのワニスで画面に光沢を出して、深い色でより色彩表現の効果を高めたい。
5. 腕鎮
今回新たに、腕鎮を使ってみた。手の置き場、拠り所ができて安定させることができる。これはとてもよい、とても使える代物だ。色を塗る際、輪郭線を引く際、その精度を飛躍的に高めることができる。これからの絵画制作に欠かせない道具となった。
6. 制作過程の記録
制作過程を逐一スマホで撮影して記録を残していく。絵はただ描くだけ、描いておしまいではなく、どのような過程を経て完成したのかを後にしっかりと検証し、考察を行い、理論として自分の中で定着させなければならない。それによって、制作していく度に進化していくのである。
おわりに
以上、思いつくままに書き連ねてきたが、これらが今後の絵画制作の基本方針となる。すでに次の作品の構想もあり、一気に加速していく。
社会人第3章の画業の始まりをここに宣言し、記す。
2025年2月23日
2作目を描き終えて
早くも、社会人第3章の2作目となる作品を描き終えた。今回新たに試した手法などもあるので、書き記す。
1. 型紙の使用
マスキングテープと共に、一部型紙を使用して白ヌキをしてみた。複雑なフォルムでは難しいが、基本的な幾何学図形であれば可能だ。
輪郭線を引かないので、きれいな白ヌキとなり、その後の描画が自由になるが、それは同時に目安となる線がないことも意味する。モティーフの内部のパーツが複雑な場合はまた考える必要があるが、マスキングテープでは難しい白ヌキには型紙が有効であろう。
2. マスキングテープの白ヌキ
マスキングテープをしっかりと圧着させると、きれいに白ヌキでき、色がこんもりと盛り上がって立体的に感じられる。ここまでのクオリティの白ヌキがつくれれば、後の作業も楽に、そして精度を高めて行うことができるだろう。
ただし、マスキングテープだと境目のみ保護されるため、勢い余ってテープを乗り越えてしまうと、白ヌキ部分に色がはみ出してしまう。この欠点を克服するために、型紙との併用も視野に入れて考える必要がある。
3. 面相筆による線描
これが目下最大の課題である。線描には面相筆を用いること、そして筆で線描する際は、鉛筆やペンとは異なる持ち方をする必要があるということを、今回新たに学んだ。斜めではなく、支持体に対して垂直になるよう筆を立てて持ち、筆先を360°自在に動かせるようになることが肝要である。
親指を支点にして、人差し指でコントロールさせると、円もきれいに描けるという。力を入れ過ぎず、ダラーンと弛緩させる、天井から糸で吊り下げられた振り子のように、くるくると動かすのがコツのようだ。
とはいえ、クロッキー帳に練習でいくら線を引いたり、円や三角、四角などの図形を描いてみたところで、本番はなかなかうまくいかない。注意していないとすぐに筆が傾いてくるし、筆先のコントロールが効かずに思い通りの線が引けない。それでも、特に円を描く動作においては、なんとなく間隔を掴みつつある。
今後は、とにかく面相筆で思い通りの線が自由自在に描けるように、日々鍛錬、日々精進していくしかない。
2作目を描き終えて、社会人第3章の作風は新たなものになると確信した。
2025年2月25日
写すな、創れ。感じるな、考えろ。
絵は、目で見た通りを描くことではない。視覚上はそのように見えるかもしれないが、それは物や事の表面にすぎない。見たものを一度頭の中で整理して、その構造や本質、特性を分析し理解した上で、絵として表現しなければならない。つまり、写すな、創れ。ということである。
写すだけなら、写真の方がよっぽど優れているし、最新の技術であるAIなどにはとうてい敵わない。そうではなく、人間が勝っているのは、自分で編集して創ることができるという点だ。理論的、数学的な正しさよりも、絵の中の世界として正しいことを描いていくべきである。
言い換えればそれは、感じるな、考えろ。ということである。感じる(見たまま写す)のではなく、考える(頭の中で創る)ことが重要だ。絵とは、本能や感情に従って描くのではなく、理論と知性で解釈した結果を描いていくものである。
社会人第3章の画業は、これをモットーとして描いていくこととしたい。
――写すな、創れ。
感じるな、考えろ。
2025年2月25日
第23冊ノートを終えて
無敵のチー牛として生きていく覚悟を決めて書いたこのノートであるが、髪をグレーに染めてみたり、アームカバーとツーブリッジの金縁メガネをかけてみたり、そのような変化を記録することとなった。
そのように、いわば変身して病気休職から復帰し、仕事の方はもう最低限のことしかやっていないが、創作はかなり充実したものとなった。百首百枚の短歌を詠み、描き、絵画の制作手法について研究を重ねてきた。さらに、人生で初めて沖縄に行くなど、この間は相当に内容の濃い日々であった。
そして、社会人第3章の画業も始まった。1年以上、どの作品をもって次の段階になったとすべきか悩んでいたが、ついにその時がやってきて、幕が上がった。新たな作風、新たな手法によって、あれも、これも、それも、なにもかも、すべて描いて描いて描き尽くしてやる。新たなモットーは、「写すな、創れ。感じるな、考えろ。」である。
次のノートからは、社会人第3章の画業として、実践と考察の研究、短歌や俳句、定型詩を詠むための推敲、その他諸々が書き殴られたネタ帳と化していくだろう。
2025年2月25日 プラス思考でCoya